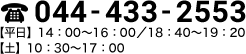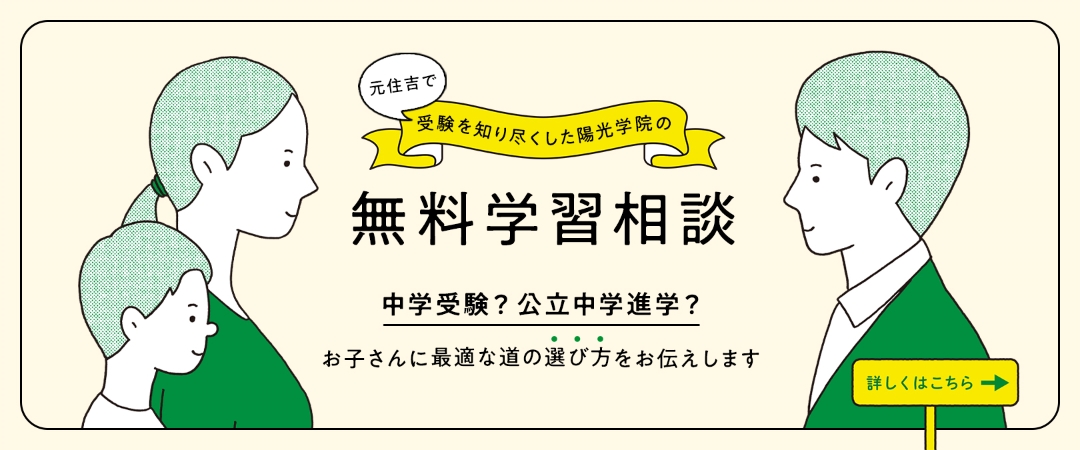受験ナビチャンネル
-
入試③:私立第一志望の入試(10分11秒)私立高校を第一志望とする場合、推薦入試またはオープン入試での合格を目指します。【推薦入試:内申点や出席状況などの出願基準を満たす必要があります】 【オープン入試:基準を問わず、試験結果で合否が決まります】 まずは各校の出願基準をクリアすることが基本です。ただし推薦入試には「不合格になるかもしれない推薦入試」もあるため、併願校の検討が欠かせません。本動画では、試験日程や私立併願の可否、出願から入学手続きまでの流れについて詳しく解説します。
-
R6年度入試速報(19分31秒)2024年度の公立高校入試要項が発表され、各高校が合否の決定に際して重視する項目が明らかになりました。いずれにしろ内申点と学力の両方をバランスよく高める姿勢で取り組むことが大切です。また今年度より面接が廃止されましたが、橘高校では例外的に面接が実施されます。面接がない高校であっても、受験する学校の特徴を十分に調べておくことが重要です。本動画では、最新の入試情報と注意すべきポイントについて解説します。
-
入試②:公立トップ校(12分41秒)公立トップ校の合格ラインは非常に高く、主要5科目に加えて技能教科でも高い評価が求められます。また学力検査の得点勝負にも打ち勝つ必要があり、総合力が試される入試です。さらに、公立トップ校では「特色検査」が課される場合があり、通常の学力検査に加えて独自の対策が必要となります。本動画では、合格に向けた早期の準備や具体的な学習計画について解説します。
-
入試①:公立第一志望(11分39秒)公立高校を第一志望とする場合でも、私立高校を併願するのが一般的です。ただし受験する私立高校が増えるほど、過去問対策などの学習負担が増えるため注意が必要です。特に元住吉周辺は交通アクセスが良好で、乗り換え1回以内で選択肢となる高校が多くあります。その反面、広い地域から受験生が集まるため、県平均よりも倍率が高くなる傾向があります。本動画では公立高校第一志望の場合の入試戦略について詳しく解説します。
-
内申④:主体的に取り組む態度(12分10秒)2021年度から「主体的に学習に取り組む態度」が内申点の評価基準の一つとなりました。この評価はテストの点数とは別の視点で判断され、学校生活全般に関わる重要な要素です。お子様自身が「なぜこの取り組みが必要なのか」を理解することが、学習姿勢の向上につながります。本動画では、この評価基準の具体的な内容と、どのように取り組めばよいかについて詳しく解説しています。
-
内申③:観点別評価の評価基準(13分11秒)高校受験で使用される5段階の評定は「観点別評価」を基に決定されます。この観点別評価を正しく理解し、時には学校の先生に質問することで、今後の学習方針が明確になります。全教科に共通して重要なのは 「努力の上限を作らない」「提出期限や評価基準を把握して確実に課題を遂行する」ことです。これらのポイントを意識して内申点を向上させましょう。
-
内申②:評定のつき方(8分39秒)内申点を構成する3つの観点を分析すると【努力すべきポイント=具体的な学習方針】 が見えてきます。観点別評価は、先生からの「ここを頑張ろう!」というメッセージです。最高評価の「5」を取得するためには、3つの観点すべてで高評価を得る必要があります。本動画では、テスト、レポート、授業態度など、すべての面でバランスよく評価を上げる方法について解説します。
-
内申①:公立/私立入試における内申(18分8秒)公立高校の入試はもちろん、私立高校の推薦入試や併願優遇制度でも内申点が選考基準として重要視されます。特に私立高校の中には、定員の8〜9割が内申点のみで合格が決まる学校もあるぐらいです。現在の絶対評価制度では、かつての「オール3」に相当するのは「4が半分程度」の成績に該当します。本動画では具体的な内申点の目安と、その重要性について詳しく解説します。